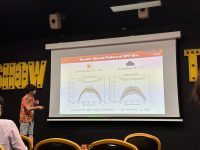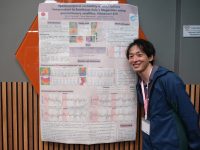千葉大学環境リモートセンシング研究センター(CEReS)が推進する日本学術振興会 研究拠点形成事業(先端拠点形成型)「静止気象衛星観測網による超高時間分解能陸域環境変動モニタリング国際研究拠点」(コーディネータ:市井和仁教授)は、2025年8月1日~2日、シンガポールにて第3回国際ワークショップを開催しました。
本ワークショップは、今年度から新たに参画したシンガポール国立大学のXiangzhong Luo准教授がホストを務め実施され、シンガポール・クラークキー地区の会場には日本・アメリカ・中国・韓国・オーストラリア・ドイツ・インドネシア・シンガポールなど、これまでで最も多様な国から研究者が集まりました(図1)。現地参加42名、オンライン参加約20名と過去最多の規模となり、特にヨーロッパからの研究者による発表は、本分野への国際的関心の広がりを示すものとなりました。また、日本からは千葉大学(市井・山本研究室および楊研究室)より12名、筑波大学から1名、京都大学から1名が参加し、国内研究者による積極的な貢献も見られました。

本プロジェクトでは、ひまわり8号をはじめとする各国の静止気象衛星を活用し、地球規模での陸域環境の高頻度モニタリングを進めています。すでに4年目を迎え、千葉大グループでは地表面反射率や地表面温度、アルベドといったデータを構築し、コミュニティに提供できるようになり、研究ネットワークが広がりつつあります。地表面温度やアルベド、光合成量などのデータは、気候変動対策や災害対応、農業管理にも活用可能であり、今回の会合でも乾燥域や熱帯雨林における最新の応用成果が共有されました。また、若手研究者や大学院生による発表も多く行われ、次世代育成の場としても大きな意義を持つ会となりました。

恒例となった開催地オリジナルの広報ポスター(図2)は、市井研究室の小菅生技術補佐員によって制作され、会場を盛り上げました。今回の開催にあたり、多大なご尽力をいただいたシンガポール国立大学のLuo准教授と研究室メンバー、そして千葉大学CEReSの藤田さん・小菅生さんに深く感謝申し上げます。
さらに、本プロジェクトは今後、国際的な研究ネットワークを一層拡大し、2026年5月下旬に千葉で開催される日本地球惑星科学連合(JpGU)とアメリカ地球物理学連合(AGU)の合同大会と連動する形で、第4回国際ワークショップを開催することとなりました。次回は、研究成果のさらなる発信に加え、世界各国の参加者に「研究面でも交流面でも楽しんでいただけるワークショップ」を目指し、本拠点チーム一丸となって準備を進めてまいります。
(千葉大学 教授 市井和仁)