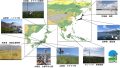8月4日から8月22日までの三週間、シンガポール国立大学(National University of Singapore; 以下NUSと記載)のXiangzhong Luo(Remi)准教授のもとに滞在し、共同研究を行いました。NUSは規模が非常に大きく、世界中から学生や研究者が集まる国際的な大学です。キャンパスは広大で、学内はバスで移動する必要がありました。自然にあふれていたこともとても印象的でした。
Remi准教授の研究室では、主に①モデルなどを用いた炭素循環評価、②衛星リモートセンシングデータを活用した東南アジア域や全球スケールでの植生変動解析、③フィールド観測やフラックス観測による光合成量推定やモデル検証、の三つの研究テーマが進められています。特に②の東南アジア植生解析は私の研究テーマと近く、これまでも学会やワークショップを通じて議論を重ねてきました。
今回の滞在では、ひまわり8/9号の観測データを用いて、エルニーニョ現象や正のIndian Ocean Dipole現象時に東南アジア域の植生がどのように変動するかを明らかにすべく解析を行いました。ひまわりデータはその観測頻度の高さから膨大なデータ量を有し、外部から数年分を扱うことには困難が伴います。そこで、データに容易にアクセスできる私が解析を担い、Remi准教授の豊富な知見のもとで研究を進めることで、双方にとって有益な成果を得ることができました。その結果、論文投稿に向けた準備段階に至るまで研究を進展させることができました。

研究室での生活は、単独で国外の研究室に長期滞在するという経験をこれまでしたことがなかった私にとって、大変貴重かつ刺激的なものとなりました。研究室にはシンガポール、中国、インドネシア、香港、イギリス出身のメンバーが在籍しており、すべてのやり取りが英語で行われます。ゼミでは毎回二名が発表形式で進捗を報告し、その他のメンバーも一週間の成果を共有します。ここで驚いたのは、全員が共有するのに十分な量の進捗を毎週生んでいることです。特にポスドクの方々は研究のスピードが速く、常にNature系列の論文を目指す姿勢には大きな刺激を受けました。私自身も発表を行いましたが、周りの高いクオリティの発表と比較して、英語でのプレゼンテーションスキルの向上が今後の課題であると再確認しました。
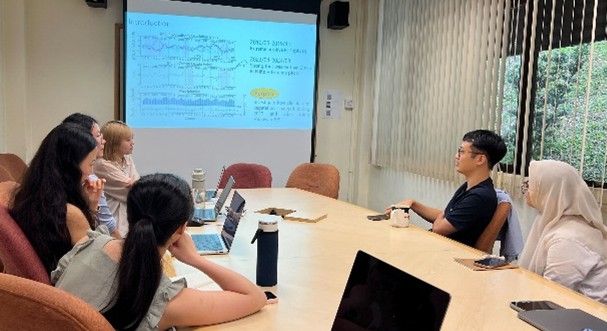
研究室メンバーとの交流も非常に充実していました。15名ほど所属している研究室のうち大半が女性という特徴的な環境の中、学生・ポスドクの区別なく仲が良く、私にも大変フレンドリーに接してくれました。滞在中には歓迎会と送別会を兼ねたGroup dinnerが2度開催され、一度は写真を撮り忘れるほどメンバーとの時間を楽しむことが出来ました。他にも、大学内に多数あるCanteenで毎日昼食・夕食を取ったり、学生寮が多くあるU townに行ったり、卓球をしたり、大学内のNatural Museumで様々な展示を見たり、自国のお土産をくれたりと、多くの機会を通して親しくなることができました。三週間という短期間ながら別れを惜しく思うほどの関係を築くことができ、今後もこのつながりを大切にし、将来的に機会があれば共同研究に発展できればと願っています。


昨年のNASA Ames訪問に引き続き、このような貴重な経験をさせていただき、この場を借りて心からの感謝を申し上げます。今回の滞在で学んだ高い意識を持って研究に臨む姿勢を忘れずに、成果につなげられるよう一層努力を重ねます。そして、再び訪問できる日を目標に研究に励みたいと思います。
(千葉大学 市井研究室 M2 長谷美咲)